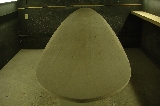![]()
サーフボードの素材は"軽量化と防水"をテーマに進化してきました。
言い換えると、"乗り易さと耐久性"の追求の歴史です。
その中で、ウッドはどのように進化して来たのでしょうか?
![]()
- 大木から削りだした"Solid"ボード。
- 一度サーフボードの形に削った木材を板状にスライスして、 中をくり貫いた後に、元の形に貼り直した"Chamber"ボード。
- 骨組みに薄い外板を貼り合わせ形にする"Hollw"ボード。
このような木製サーフボードの軽量化の技術は、船、ボート、カヌー、カヤック等の
”木材を使った、水の上を滑る乗り物”の進化と共にあります。
”西暦400年頃には、古代ポリネシア民族が、漁の帰りにボートを用いて波に乗る術を知り、
そこから木製の板に乗るようになった。”
”西暦1700年代、キャプテンクックが船でハワイに着いた時、
夢中で波に乗っている地元民がいた。” など、
既にサーフィン史の文中、絵には、サーフボード以外の木製の乗り物が出てきます。
創世記のシェィパー達はそれらの技術を取り入れて、より軽い乗り味を追求していきました。
丸太をくり貫いて形作る"くり舟"を、中空になるように貼り合わせることによって、
"Chamber"サーフボードになり、 "くり舟"の外壁に木の板を継ぎ足し、補強の骨組みを付けた
"ボート"や"カヌー"等に、上から蓋をすることによって、"Hollow"サーフボードにと、
それぞれ進化していきました。
![]()

1950年代に、Bob・Simmons(ボブ・シモンズ)と
Hobie・Alter(ホビー・アルター)、そして仲間数名で、
発泡させたPolystyrene(ポリスチレン)を心材にして
エポキシFRPで防水・補強する製作技術を発表しました。
その頃のウッド・サーフボードは、軽量なバルサの木を使い、
ポリエステルFRPでコーティングする方法が主流でしたが、
それには問題点がありました。
- アメリカ本土で使えるバルサが少なくなり、
安定供給が難しい状況になってきた事。
- バルサ材に限らず、木材の水分や"やに"がポリエステル樹脂との相性が悪く、
剥離しやすい事。
- 水がボード内部に入ると、すぐにバルサ材が腐り易い事。
その後、研究を重ね、発泡ポリウレタンをサーフボードの心材とし、
ポリエステルFRPで防水・補強する方法に辿り着きました。
軽くて、シェィプしやすく、安定供給、大量生産できる。
サーフィン史の中で、革命的な出来事でした。
それ以降、ウッド・サーフボードはほぼ絶滅し、表舞台に出る事はなくなりました。
一方、木製の船やボート達はと言うと、同じように科学の波に押されて、
安くて生産性の高いポリエステルFRPそのもので形作ったり、
鉄などの工業製品になりましたが、細々と進化・発展していきました。
![]()
2005年12月5日に、サーフィン界に事件が起こりました。 フォームブランクスの最大手
”クラークフォーム社”が突然事業を止めてしまったのです。
様々な廃業理由の一説に、発泡させる際に使う化学薬品"TDI系イソシアネート"の
毒性による環境・人体への影響がありました。
これをきっかけに、"軽量化と防水"がテーマだった進化に"環境対応"へのバランスが
要求されるようになり、世界中から将来へのサーフボード素材開発が始まりました。
開発は大きく2つの方向に進み、より科学的な解決と、自然素材を使用する道です。
前者は、毒性の少ない"MDI系イソシアネート"に切り替えたり、
その"MDI系イソシアネート"に、植物由来の原料を混ぜて発泡させる植物系ブランクスや、
リサイクル可能なEPSフォームを使ったボード、中空のカーボンボードなどがあります。
後者は、木製のボート、カヌー、カヤックなどの伝統的な木組み技術と、
進化した接着剤や防水用樹脂によって、木材を使ったサーフボードが注目され始めました。
また、アライヤ等FRPを使わない木製の道具達も見直され始めています。
今後は、環境に配慮した様々なサーフボードが出てくる中で、
ウッド・サーフボードは選択枝の一つとして、進化し続けるでしょう。